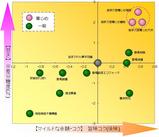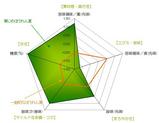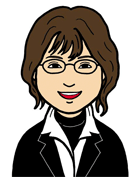安全寺という地域
2010年1月31日 14:12
男鹿半島に安全寺という地名がある。ナビにも掲載されている。いったいどんな場所なのか。
安全というニュアンス、寺という神社仏閣系の癒しのムードが相まって、さてどんな場所かと空想は膨らむ。寺は「駆け込み」などのレスキューのイメージがあるし、神社であれば祈願系、交通安全祈願の地域・・・だけど、寺?右手に冬の日本海のダークな海外線を横目にしながら頭の中は脈絡の無い空想でぐるぐるしている。
安心と安全は昨今の食の課題。
偽造を見抜くとか消費者センターだとか、食品安全委員会だとか、つねに危うく信用できない世界、というのが前提となっているような気がする・・・ちょっとせちがない。
古来、胡椒のとりひきに砂が混ぜられていたとか、所詮、利益追従だとプライドなんか二の次かもしれない。
安心は気持ちの問題だから100%の安心はある。
安全は確率であるから100%の安全は存在しない。
お会いした農家さんは、とってもこころ優しいおかあさん。おかあさんの畑は冬の寒さでもじっくりゆっくり育つ、やわらかな食感と味の「葉やさい」さん達。その場でつまんで食して「おいしい~っ」。おかあさんと畑に立つと、ルンルン・ふわふわ心弾んで、子供の頃にもどったよう。自分のおかあさんと過ごす安心の時間、そんなときもあった。
しかし、この畑脇に道路が出来たとたん、農作物を無断でもっていく不届き物がいると聞いた。おかあさんは笑って話しているが、立派な犯罪である。その点では安心、安全では無い。また頭の中がぐるぐるする。おまわりさん、地域の安全よろしくお願いします。
おうちに案内していただいて、お手製のおやきをご馳走になる。あったかくて甘くって、同行のかたと二人が子供で、おかあさんにおやつをもらっているようなムードだ。
そして「なた漬けのナタ」は立派な調理器具なのです。怖くないこわくない。
おじいちゃんが安全寺の地名を解説してくれた。盗賊の目に付かないひっそりと小さな集落。安全地域とか安全地帯の地名にすると、人々が安住の地を求めて殺到してくる。寺ならそんなイメージは生じない、というのが理由との事だ。安全という地名にこだわるのは、信仰とか願い、祈りみたいなものが込められているのだろう。
おうちの柱に張ってあったお孫さんあるいは曾孫さんのスナップ写真。おかあさんもおじいちゃんも、このお家も、きっとみんなの安全寺なんだと思う。
後日、今回訪問時撮影した写真をお送りした。おかあさんは以前たばこの葉の栽培をしていた。メロンや野菜の栽培に切り替えたものの、未来に対して少々不安を感じているとお話ししていた。しかし写真のお礼を綴った手紙には、そんな不安など感じさせず、生きていく希望に満ち溢れていた。
おいしいものを作っていることによって、それを理解して下さる方々が、必ずいらっしゃるという事、確実に感じました。(原文のまま)
野菜王・・・・脳裏をよぎった。きっと何処かに野菜王はいる。
ラベル: 総合